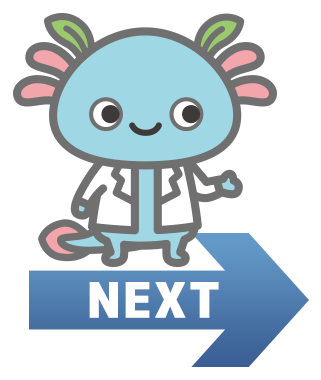「沈黙の臓器と呼ばれる肝臓は、私たちの健康に非常に重要な役割を果たしています。
しかし、脂肪肝やウイルス性肝炎など、様々な原因による肝機能障害を抱える方が増えています。
従来の治療法は、生活習慣の改善や薬物療法が主流でしたが、近年は新たな治療法として「再生医療」も注目されています。
肝機能障害の従来の治療法
肝機能障害の大部分である肝炎や肝硬変がウイルスによるものであれば、肝炎ウイルスに対する薬物療法が最も重要です。
抗ウイルス薬によって肝炎ウイルスを排除したり、ウイルスの増加を抑えると肝臓の炎症は治まります。
その結果、肝線維化の進行が止まり、肝がんが発生するリスクも低下します。
また、時間はかかりますが、肝臓に溜まった線維が溶けて硬くなった肝臓が元に戻ることもあります。
抗ウイルス薬が効かない場合や使用できない場合には、肝細胞が破壊されるのを抑える薬を内服、または注射で投与する肝庇護療法を行います。
体内の鉄の量を減らす瀉血(しゃけつ)療法も肝細胞が破壊されるのを抑えるのに有効です。
自己免疫性肝炎では、免疫の力を抑えるために副腎皮質ステロイドを投与します。
また、脂肪性肝炎では、禁酒や食事療法と運動療法による体重制限が最も重要な治療法です。
これらの治療で改善しない場合は、薬物療法を行う場合もあります。
- 抗ウイルス薬による薬物療法
- 薬の内服
- 注射の投与
- 瀉血(しゃけつ)療法
- 副腎皮質ステロイド投与
- 運動療法
肝機能障害に対する再生医療の期待される効果
再生医療のひとつ「自己脂肪由来幹細胞治療」を用いることで、免疫拒絶を伴わないことが考えられます。
複数回の処置が可能で、大きな手術を必要とせず経静脈・動脈投与が可能となります。
比較的低コストで行えるなどのこれらの現状を受けて,肝移植を補う非侵襲的な治療法として自己脂肪由来幹細胞治療が期待されています。
幹細胞治療の流れ
1.問診および術前採血
医師が治療の特徴と期待される効果などを説明致します。必要に応じて検査を受けていただきます。
2.脂肪採取および培養用の採血
腹部から脂肪を採取します。術後、この傷はほとんど目立たず、痛みもほぼありません。
採取自体は数分で終了します。また、同日に培養の行程に必要な血液を採取します。
3.培養
組織採取後すぐに、CPC内にて細胞培養を開始し、治療に必要な数まで増やします。全行程はCPC内にて行われ約4-6週間の期間を要します(個人差があります)
※患者様によって若干前後しますのでこの時点では投与日は確定できません。
※培養過程で異常が認められた場合は培養を中止することがあります。

4.ご連絡
細胞培養開始約2週間後のある段階で残りの培養に必要な期間が確定します。
ここで投与日(治療日)をご相談の上、確定させていただきます。
細胞投与を最適な条件で行うために、一度確定された投与日(治療日)は原則として途中変更できません。
5.投与(治療)
確定させていただいた日時に治療を行います。
場合によっては麻酔を行った後に注射を行います。
6.術後
静脈投与の場合、術後まれに腫れることがありますが、ほとんどの場合程度は大きくありません。
念のために消炎鎮痛剤を少量お渡しします。
※若干の内出血を来すことがありますので、当日の長風呂や過激な運動はお控えください。
7.投与後の治療スケジュール
一度の治療で効果を実感されている方が多いですが、さらに効果を望まれる場合は複数回注射することをお勧めします。
まとめ・肝機能障害を治すには|新たな治療法「再生医療」について
肝機能障害に対する幹細胞治療で、肝臓の働きが修復される可能性があります。肝機能障害は、適切な治療によって改善することができます。肝硬変になる前に、早めが「肝心」!定期的に健康診断を受けるなど、早めの対策を心掛けましょう。
従来の治療法に加え、近年は新たな治療法も開発されており、治療の選択肢は広がっています。最新の治療法「再生医療」も選択肢のひとつとしてご検討されてみてくださいね。